
TEL 06-6447-4680(代表)
HOMEコレクション&リサーチ中之島映像劇場アーカイブ第22回中之島映像劇場 映像のアルチザン—— 松川八洲雄の仕事 ——
| 1 | 映画の「解放」をめざして——松川八洲雄の「ドキュメンタリー」観 森田 のり子 |
|
|---|---|---|
| 2 | アルチザンの修行時代—— 1960年代の松川八洲雄 まつかわ ゆま |
|
| 3 | 松川さんに惹かれて 日向寺 太郎 |
|
| 4 | アルチザンのまなざし 田中 晋平 |
森田 のり子
日本のドキュメンタリー映像史の系譜をたどろうとする時、松川八洲雄はその歴史的位置づけが容易ではない作り手の一人である。それは表層的に捉えるならば、彼が若き日に松本俊夫・黒木和雄・土本典昭といった面々と問題意識を共有した表現活動を展開しつつも、そうした人々の多くがPR映画に可能性を見いだせずに自主製作映画へと向かっていったなかで、晩年までPR映画を意欲的に作り続けたという点に起因するであろう[1]。
しかし一方で、実のところ松川はそうした仲間の中でもひときわ「ドキュメンタリー」という領域に思い入れを持っていたのではないかと感じさせられる節がある。その根拠となりうるのは『ドキュメンタリーを創る』と題された著書の存在だ[2]。農山漁村文化協会が刊行する「人間選書」シリーズの一つとして1983年に松川が書いたのは、あらゆる映画表現の可能性に根ざした上で自らの実践内容に徹したドキュメンタリー制作論であった。今回はこの著書を手がかりにしながら、松川が「ドキュメンタリー」に何を求め続けていたのかということについて若干探ってみたい。
まず、彼の基本的な姿勢は冒頭の「なぜ本書を書いたか—「まえがき」にかえて」の時点で明快に記されている。松川は「ドキュメンタリー映画の作り手たちの多くが、(中略)素材をそのままフィルムに移しとって見せるのを、何か新しいドキュメンタリーの方法であるかのように思い込んでいるのにいらだたしい気がしていた」(3頁)と打ち明ける。これに対して「作り手の思想、あるいは考え方は、はからずも作り手の〝見方〟〝とらえ方〟といいかえられるように、具体的な〝方法〟のありように拘ってくる」(同)と指摘した上で、「多種多様な素材やテーマを、ぼくはその素材やテーマに引きずられずに、自分の思想、あるいは考え方、見方、捉え方で自分の映画にしてきたと思っている」(同)と言い切る[3]。そして実際に、4章立ての本文において自らの「思想」「考え方」と「具体的な〝方法〟」の両面をパラレルに綴っていくのである。
その大まかな流れを説明しておけば、自己の経歴と映画史とを重ね合わせて振り返る第1章「映画=可能性をはらんだ芸術」、編集・シナリオ・ナレーション・撮影・スタッフワーク・音楽といった実践のあり方を多彩な自作の例を通して記した第2章「実作による記録映画入門」、なかでも異色の自主制作となった《不安な質問》の構造にフォーカスした第3章「自作「不安な質問」の映画製作法」、そして映画表現の原点を確認しつつ自らが目指すドキュメンタリーの方向性をまとめた第4章「記録映画の思想と方法」である。読みものとしては第2・3章の具体的な制作をめぐるエピソードが魅力的だが、ここでその仔細に立ち入ることは叶わないため、今回はむしろ第1・4章から垣間みえる松川の「ドキュメンタリー」観と、そのヒントになりうる第2章の第1節「編集」と第6節「カメラマンについて」を取り上げて考えてみよう。
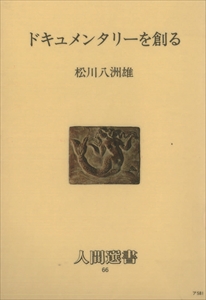
第1章では、松川が芸術と映画に興味を惹かれていった経緯を社会の変遷とともに簡潔にまとめているが、そのなかで最初に具体名を挙げているのがセルゲイ・エイゼンシュテインの《戦艦ポチョムキン》(1925年)である。松川が生まれる6年前の作品という形で言及されており、「映画を見世物の発明品から人間の認識の重要な様式へと形をととのえさせた傑作」(13頁)と非常に高く評価している。そしてこれ以降、同書には何度かエイゼンシュテインの名前が登場し、松川にとって重要な存在であることを示唆するのである。一方で、子ども時代に直接的な影響を受けた作品としては文化映画の《或る日の干潟》(1940年/演出:下村兼史)を挙げ、「一本の映画が一人の少年の心に焼きついて一生残る」(15頁)という経験をしたとも記している。
敗戦後の青春時代には、東京大学で現代絵画に関する卒論を書く傍らでイタリア・フランス・ポーランドなどの作品に親しみ、短編映画プロダクションの仕事を始めてまもなく、ジャン=リュック・ゴダールの《勝手にしやがれ》(1959年)に出会って衝撃を受けたことを綴っている。そして、同じくヌーヴェル・ヴァーグに「魅了」(22頁)された仲間とともに5年にわたって活動した「映像芸術の会」に触れ、末尾には世界/日本映画史に自作の歴史を重ねた「ぼくなりの映画史年表」を掲載している。興味深いことに、この章ではイギリスのドキュメンタリー理論を「PR映画の理論的根拠」(21頁)になった「かたくなで痩せた〝事実〟主義」(22頁)として批判しているほかは[4]、それほど「ドキュメンタリー」という言葉に比重が置かれていない。
そのような感触を持って第2章に進んだ際に印象的なのは、第1節で「編集」を論じていることである。松川は「ぼくにとって映画とは、〝映像で語る〟あるいは〝映像によって表現する〟芸術に他ならない」(40頁)とした上で、「映像の言葉を最大限にひきだすのが、編集の仕事」(同)であると位置づける。そして、撮影した全カットを絵コンテに起こして縦方向に切り貼りするという独特の編集テクニックを紹介していく。この手法は《鳥獣戯画》で絵巻物を撮影対象にした際に体得したものだというが[5]、まず何よりも画面一つひとつの組み合わせが優先されるという松川の制作スタイルを端的に示しており、そこには彼が吸収してきた戦前期の映画や美術作品との親和性もうかがえる。
一方で、実際の制作過程において編集の前に不可欠な「撮影」に松川が言及するのは第6節まで待たねばならない。しかも、ここで取り上げられるのは自らのポリシー以上に、多くの松川作品を手がけてきた瀬川順一というカメラマンのエピソードなのだ。松川にとって「撮影」とは明らかにカメラマンの仕事であり、自身の役割はその相手とのコミュニケーションに尽きるという考えがよく表れている。そんな彼の瀬川順一論にも、注目すべきポイントがある。瀬川は戦時期の東宝文化映画部からキャリアを始め、有名な《戦ふ兵隊》(1939年/演出:亀井文夫)で名カメラマン・三木茂の撮影助手についた人物であった。松川は、この三木による「カメラマンは映像を表現の手段とした映画作家である」(145頁)という「カメラマン演出説」(151頁)を瀬川が受け継いでいると評した上で[6]、《戦ふ兵隊》のように国策とは異なるメッセージを発する暗喩的なカットを撮った三木には「批評の目」(144頁)が備わっており、その助手であった瀬川も「映像の中に批評をこめること」(同)を学んだのではないかという。そして、ソ連帰りだった亀井がそれらのカットを生かして複雑なモンタージュに仕上げたのを引き合いに、瀬川のことを「エイゼンシュタインの孫弟子だったのではないか」(同)と記すのである。むろん、それは松川ならではのウィットには違いないが、彼が撮影段階から編集段階まで一貫して映像による重層的な意味生成に強い関心を寄せていたということをあらためて感じさせる。それを踏まえてみれば、松川が「イメージ・イーター」(151頁)と称したように、緻密な画面を作り込んでいくことで知られた瀬川との相性の良さも頷けるのである。
ここで、ちょうど瀬川とタッグを組んだ最初の一作として紹介されている《仕事=重サ×距離》に着目し、その記述内容と映像表現を照らし合わせてみよう。この作品は、当時の造船業界において世界最大級を誇った三菱重工業・長崎造船所による求人用PR映画で、製作会社はまだ新興企業であった日本リクルートセンターである。高卒入社の青年労働者らの朝の始業から夕方の終業までの一日を描いており、全編にわたって高度経済成長期の生産現場を支える、松川いわく「労働に誇りをもった労働者らしい若者たち」(154頁)の活気が捉えられている。
その撮影にあたって松川は瀬川とは打ち合わせをせず、青年労働者らの職場をまわって話を聞き、シナリオ代わりに散文詩のような「労働讃歌」を書いて瀬川に託したという。そして、瀬川は「それを読みとり、映像という躍動をもった言葉で美事に応えた」(149頁)のだった。実際の作品を観てみると、カメラを見つめる若々しい顔、厳しい環境でのタフな仕事ぶり、お昼休みのひととき、広大な造船設備、悠々と進水する完成船といったカットが丁寧に重ねられ、臨場感が伝わってくる。その一方で、青年らによる肉声は映像から切り離され、岸田今日子による詩的なナレーションと同格の扱いでさまざまなシーンに散りばめられている。そして、これらの声はときに映像のなかの彼らを裏切るように、「本当は板前になりたかった」「自動車以上に神経を使う」「土曜日の晩が一番楽しみ」と、その単純ではない心情をも打ち明けている。ここでは映像と音声がランダムに組み合わされることで、一人ひとりの顔や一つひとつの声はヴィヴィッドでありながらも、あえて対象の固有性まで突き詰めずに余白を持たせたイメージでまとめていく構造になっているのだ。
むろん、自らの青年期にはストライキや労働組合に積極的に参加したという松川が1970年代の労働者らの日常生活に立ち会うなかで[7]、その順応的な面だけにしか興味を覚えなかったとは考え難い。実際、彼はこの作品のテーマに関して「労働とその成果についてであって、その分配については触れていない」(145頁)と自覚的に記している。しかし、松川はかつての土本や黒木のように、労働者らの課題や悩みを取り入れようと試みてスポンサーと衝突するといった道は選ばなかった[8]。こうした松川の特質については、同時代において主流となっていた「ドキュメンタリー」には囚われない視点から再考してみる余地があるはずだ。
著書の締めくくりとなる第4章「記録映画の思想と方法」において、松川はやはり「ドキュメンタリー」を迂回してみせる。自作《不安な質問》とエルマンノ・オルミの《木靴の樹》(1978年)の共通点から記録/劇という境界線を問い、1960年代のゴダールの革新性をキュビスムの観点から論じ、テオ・アンゲロプロスの《旅芸人の記録》(1975年)の長回しに内包されたコラージュの手法に注目する。そして、あらためて大学時代の卒論で用いた文献から1920年代のソ連に言及し、そこでは映画があらゆる既存のジャンルや固定観念から「解放」(241頁)されるものとして期待を集めていたことを挙げ、「もし映画がエイゼンシュタインのみつめる方向に疾走していたら、どのような地平を切り拓いていたろうか」(同)と投げかけるのである。
松川は最終的に、「映画が資本主義の申し子として生まれながら、その可能性の芽のほとんどが資本主義そのものによってつみとられ」(260頁)たために「映画の映像の可能性は、依然としてほとんど萌芽のまま凍結している」(261頁)とまとめている。その上でやっと、「ぼくがドキュメンタリー映画を選んだのは、商業資本や興行資本、分業化やスターシステム、撮影所やシナリオからはるかに自由であると思えたからであった」(261頁)と率直に記している。彼の著書はその映画作品と同じく、年代も分野も幅広い要素からモンタージュされているがために軽妙なエッセイのような印象を与えるが、その主張は実のところシンプルである。つまり、松川は常にエイゼンシュテインの地点まで立ち返って映画の「思想と方法」を「解放」していくことを志し、そのジャンルレスな実践そのものを「ドキュメンタリー」に託していたのだ。
この文脈において資本主義のあり方を批判する一方でソ連アヴァンギャルドを評価するとなれば、そこには社会主義や共産主義への傾倒を想像したくなる面もある。しかし松川は、少なくとも映画制作の上では、そうした特定の政治体制へのコミットからも「解放」されようとしていたようだ。だからこそ、青春時代の仲間の多くが社会状況と強く結びついた自主製作運動へと打ち込んでいくなかにあって、PR映画という資本主義の内側から自らの「具体的な〝方法〟」(3頁)のみをもってそれを突き破ることに独りで挑んでいたように感じられる。それはまた、PR映画という一見偏狭な分野のなかに、松川の豊穣なアイデアを取り込むだけの土壌が培われていたということをも明らかにしている。
彼のそうしたアプローチは、正直に言って、土本や小川紳介や原一男が活躍していた時期に「ドキュメンタリー」として脚光を浴びることは難しかったかもしれない。松川の「ドキュメンタリー」は原則的に、政治運動からはもちろんのこと、撮影対象との交流や同期録音のリアリティといった戦後日本のドキュメンタリー映像史で定番のトピックからも「解放」されてしまっているからだ。むしろ、もはや現実と虚構が混じり合い、政治が文化に回収され、営利と慈善が一体となり、あらゆるジャンルが流動化している今日こそ、私たちは松川八洲雄の映画作品を新鮮な眼で見直せるのではないだろうか。
(もりた のりこ/映像文化史・ドキュメンタリー研究)
註
まつかわ ゆま
松川八洲雄は「アルチザンでありたい」といい続けた。一つの手法やテーマを突き詰めていくこと、色々な方法を試し、磨き上げていくこと。注文主が変わり、素材が変わっても、出来上がった作品はまぎれもなく「松川八洲雄印」であること。それが「アルチザン」としての松川八洲雄の仕事である。1960年代、特に前期の松川八洲雄の作品は、監督として独り立ちしたものの、まだアルチザンとして確立した手法を持たない、模索の時代であった。
松川八洲雄は、例えば同級生だった松本俊夫や後に松川原案の《とべない沈黙》(1966年)で劇映画に移行する黒木和雄のように最初から映画ファンで映画監督を目指したわけではなかった。画家を目指し、蝶マニアでもあり、大学も藝大か東大理科かと迷い、一浪後東大文学部に進学、美学西洋美術史科を選び、なおかつ大学時代には新劇劇団「ぶどうの会」演出部に所属したこともある。映画よりむしろ演劇の方が近しいという青春時代を過ごしている。
そんな松川が映像による表現に近づいていったのは同級生である松本俊夫の影響だろう。56年卒業し翌年松本に新理研映画の募集を勧められて新理研に転職し、記録映画界に入る。が、映画の作り方を学んだことも、作ったこともない。制作進行から始め、助監督にもついたが、そこで師匠と仰ぐ監督に出会ったわけでもなかった。いや、仏ヌーヴェル・ヴァーグのように世界の「新しい映画」の担い手となった1930年代生まれの若者たちは「スタジオ」や「徒弟制度」を否定して、自分たちの「新しい映画」を作ろうとしていたのだから、松川八洲雄が特別なわけではない。フランスでも日本でも、若者たちは、まず理論を構築することから始めることにしたのである。
その舞台が、1955年から始まる「教育映画作家協会」(60年に「記録映画作家協会」と改称)と機関誌『記録映画』であった。『記録映画』は58年に冊子化され、当時の記録映画作家たちの議論や理論の発表の場になった。「記録映画作家協会」は62年、社会主義リアリズムを信奉する共産党支持の権利生活派と新しい創造活動を求める若い世代に分裂する。分裂を決定づけたのは、戦前・戦中から記録映画を製作してきた人々と、戦後大学を卒業し映画界に入った若手との間で交わされた、戦争責任を巡る「主体性論争」だった。松川の言葉を借りれば「[戦中は]ほとんどすべての作家がファシズムに加担し、[彼らは]戦後いち早く占領軍の方針に従って”アメリカ民主主義”に転向した」(『ドキュメンタリーを創る』農山漁村文化協会、1983年、18頁、[ ]内引用者)、日本映画界・記録映画界に対して、戦争責任を自ら個人のもの、つまり主体的に考えるところから日本人の民主主義は始めるべきであり、創作者たるものこの主体を確保してから、主題に臨み創造活動を行うべきではないかという論争である。仕掛けたのは、松本俊夫だった。そして会は分裂。松本・松川、岩波映画製作所出身の「青の会」同人などの若手メンバーは「映像芸術の会」を結成する。64年に「映像芸術の会」が発行した機関誌『映像芸術』が新たな論戦の場となった。会員である松川もこの両誌にたびたび論文を寄せている。
特に『記録映画』1959年12月号に書いた「P・R映画とドキュメンタリー方法論の問題―人間と胃袋のためのプログラム」は松川の終生変わらぬ基本姿勢の表明であったと思う。松川は「ドキュメンタリーこそあらゆるジャンルを通じて唯一の創作方法論であると考え」(6頁)、「現実をアクチュアルに捉え、創作としてレアリテを表現する芸術の方法」(7頁)であると宣言している。PR映画をはじめとするスポンサード映画の中で、スポンサーの期待を逆手に取り、資本側が送り出す“ものが人々を幸せにする”というのはごまかしなのだという真実を暴いてやろう、ドキュメンタリーはそのためのツールとしてアートにもなりうるのだ、という宣言である。28歳の時だ。
学徒動員はされたが徴兵・学徒出陣は逃れて終戦を迎え、民主主義の洗礼を受け社会・共産主義へのシンパシーのもと大学時代を送りつつも“党”と“政治”への幻滅も経験した世代の松川八洲雄である。さりとて経済的復興をとげた“資本主義”の社会に迎合して“成功”することはよしとしない。それを個人の主体として、作品に表現していくことが、わがドキュメンタリーである、という宣言だった。
1960年、松川八洲雄の作家的実践が始まる。処女作である《印画紙の話》は「写真の持つ虚像としての幻想性をグラフィカルに描いている」(松川八洲雄『自画帖』私家版、1976年、3頁)作品だが、「真を写す」とされた「写真」が「虚像」、「幻想」であるという、「真実」と「虚構」についてのアプローチは松川八洲雄作品のテーマの一つである。続く《ハイウェイ東海道》(1961年)には蝶々のエピソードがあるが、実はこれは没になったいすゞ自動車向けのシナリオ「蝶々の旅」を応用したもので、のちの《とべない沈黙》へと続くモチーフだ。62年「実質的なデビュー作」という《一粒の麦》は昆虫採集に明け暮れた高校生物部部長の面目躍如な科学映画であり、二人のベテランのカメラマンに助けられた作品である。作品中でイラストや地図が必要になった時は自分で描くのは本作からであり、作曲家・間宮芳生との出会いもこの作品だった。

松川八洲雄(1960 年代後半頃)
1963年の《エジプト美術》は新聞社主催の展覧会を美術映画として作るという企画で、64年のやはり展覧会をきっかけに撮影された《ラス・メニナス―ピカソ展の記録》とともに、西洋美術史を専攻した元・画家志望の松川が腕を振るった作品になっている。パブロ・ピカソの手がけた《ラス・メニーナス》(1957年)は、17世紀にベラスケスが描いた絵画をピカソが解体・再構築した絵画シリーズであるが、キュビスムがリアリズムに基づく絵画の歴史を根本から変えてしまったと論ずる松川は、それと同じ変化をジャン=リュック・ゴダール映画の登場に見る論文を『映像芸術』誌に発表している。63年には《味の王様》で「味覚についての文明論」を構築していくが、これは後に「食と農と文化・文明」について考察していく作品群の出発点になった。64年には《日本のかたなとよろい》、《ある建築空間》も手掛けている。美術映画のカテゴリーに入る作品だが、《日本のかたなとよろい》は日本の伝統技術の職人としての刀鍛冶の技をとらえつつ、美術品ではなく「武器としての“用の美”」を皮肉を込めて見つめてみようという試みがなされている。職人の技を凝視する目(カメラ)による発見の力を見出したのはここからであろう。《ある建築空間》では松川自らが作るオブジェを利用して撮るなどの遊び心を見せ、映像詩と呼ぶ作風をみせている。原案と脚本、主に蝶々育成担当ということになってしまった劇映画《とべない沈黙》の制作も64年(公開は66年)だった。
1966年には《日本のかたなとよろい》に続き《文人画》、《鳥獣戯画》と東京国立博物館ものを撮っている。《鳥獣戯画》は自主作品だが、高山寺住職と親戚筋にある藤原智子監督の尽力で本物の撮影が許可された。しかし、絵巻は館外に持ち出すことはできないので、まずシナリオを書き、巻物の複製から絵コンテを描きそれに従って撮影した。しかし、シナリオ通りにカットを並べてもうまくいかない。そこで絵コンテを切り離しコラージュのように並べ直し、絵コンテによる編集を繰り返していくことにする。この方法が「アルチザン」松川の特徴となる手法になった。「今は昔」というフレーズに、映画を撮っている今現在と絵巻が描かれた昔、現実と虚構を行き来する映画という考察を重ねる《鳥獣戯画》の最後に現れる語りも、のちに何度も松川作品の柱となるテーマである。68年に撮ったのが東海テレビとの最初の作品になる《今は昔志のとおきな》。タイトル通り「今は昔」というテーマを、今現在に、桃山時代のままの方法で焼き物を焼く人間国宝の姿に託し、昔話の一節のような語りで見せていく。事実を追う「ものつくり映画」「人間ドキュメント」の常套手段を使わず、説明しないで真実をイメージさせるという挑戦をした作品である。作品が金額で評価される今に疑問を呈するシーンも松川らしい。そして69年《壁画よみがえる》と《ヘルメットの男たち》。昔を今への復元ものも松川作品には何本も見られるがその最初の作品が《壁画よみがえる》である。法隆寺金堂の焼損壁画の復元模写の記録で2年がかりで撮影された。《ヘルメットの男たち》は、建設現場で働く人々と内勤の人々に対するオールインタビューつまり事実を語る言葉で、虚構の一日を作りあげるというナレーションなしの作品。ドキュメンタリーは基本的に映像に語らせるべきという考えを実践してみた作品である。そして、70年代が始まる…。
1970年までは持続したいと粘った「映像芸術の会」は68年に解散してしまうが、ゴダール、アラン・レネ、ルイス・ブニュエル、そしてピカソ、常に変革を遂げるヨーロッパの作家たちの動向にも反応しつつ、同世代の作家たちとの誌上の論戦で構築した理論は松川の血となり肉となった。そしてそれを実践しようとするとき、現場でベテランのカメラマンやライトマンの“職人技”、音楽や音響の“創造性”に助けられ、松川の映画の骨が形成された。こうやって30代の松川八洲雄はドキュメンタリー映画のアルチザンとして地歩を固めていったのである。
(まつかわ ゆま/シネマアナリスト)
日向寺 太郎
私が松川さんの映画を最初に見たのは、今から35年前、大学三年の時だった。広島に旅行し、立ち寄った原爆資料館の展示を見て呆然としている時、館内では映画も随時上映されていることを知った。日本大学の映画学科で映画を学んでいる学生としては見なくてはという半ば義務感だった。しかし、映画が始まると、数々の肖像写真が時計の秒針の音とともに現れるファーストシーンから目を奪われた。30分食い入るように画面を見た。それが松川さんの《ヒロシマ・原爆の記録》だった。うだるような暑さの中、映画と展示物を反芻しながら、広島の街をひたすら歩き続けた。
それから少しして、大類義さんという当時映画学科の講師をしていた方から「松川八洲雄という監督の映画、見てみる?」と声をかけられた。大類さんは土本典昭監督と親しく、私を含む数人の学生と、土本さんの映画やドキュメンタリーを見る自主ゼミを開いていた。その時、大類さんは松川さんから直接十数本のビデオを借りて来たのだった。その十数本のビデオには、今回の国立国際美術館で開催する特集上映のプログラムのものは《ムカシが来た》と《出雲神楽》を除いて全てあった。この2本はその時点ではまだ作られていなかったのだ。原爆資料館で見た《ヒロシマ・原爆の記録》は松川さんの映画だったということを、うかつにもその時に知る。一本目に見たのは《土くれ》だった。映像が語るものを凝視し、耳を傾けよと言われているような驚きの体験だった。わずか18分ながら、木内克がどのような彫刻家なのか、日常の時間から創作の時間へと向かう時間の流れが描かれていた。そしてこの映画にはナレーションもインタビューもない。映画の中に言葉は存在しないのである。他にも生け花の小原流の家元小原豊雲を描いた《花の迷宮》(1986年)、六人の人間国宝を描いた《HANDS・手》(1975年)も同様だった。
私は劇映画を撮りたいと思い、映画学科に入った。亀井文夫、土本典昭、小川紳介監督等のドキュメンタリーを見ていて、凄いなあと思うことはあっても、そのような映画を自分が撮れるとは思わないし、ドキュメンタリーの道に進みたいと思うことはなかった。しかし、松川さんの映画を見て心が大きく揺らいだ。このようなドキュメンタリーだったら、自分も携わってみたい。
今回の中之島映像劇場のプログラムを見てもわかるように、松川さんの映画の題材は手仕事、民俗芸能、美術、建築、自然科学等、多岐にわたる。撮影対象に魅力があるのはもちろんだが、どの映画も面白いのは松川さんのものの見方、映画のつくり方が面白いのだと気づいた。ビデオを返しに行くという大類さんに付いて、お宅におじゃますることにした。初めてお会いする松川さんは温厚で物静かな方だったが、後に外柔内剛であることを知る。この時何を話したか、残念ながら記憶は無くなっているが、私が酒飲みであったことがよかったのは確かである。帰り際、「また遊びにいらっしゃい」と声をかけていただいた。この後、何百回と酒席をご一緒することになるとはこの時は思いもよらなかった。

長野県大鹿村にて 1991 年
大学卒業後、助監督として映画の現場に身を置きたいと考えていた私は、その後何度か一人で遊びに行き、お酒をごちそうになる中で、助監督として就きたいというお願いをした。当然のことながら、すぐにOKの返事をいただいたわけではない。しかししばらくして、岩波映画のプロデューサー・田村恵さんから電話があった。「松川さんから今作っている映画の編集助手として参加してほしいとのこと」ということだった。飛び上がるほど嬉しかった。それが1990年に完成する、人間と花の関係を通史的に描いた小原流の映画《花いける》だった。これ以降、2001年まで12本の映画に助監督として就くことになった。
松川さんの映画への思いや考え方、つくり方は名著『ドキュメンタリーを創る』(農山漁村文化協会、1983年)に充分に書かれているが、以下、私が実際に接した松川さんの独特な映画づくりを点描してみたい。
まずはシナリオである。松川さんのシナリオは、対象に何を見るか、そしてスタッフの想像力を刺激するように書かれている。私が就くずっと以前の映画であるが、特徴が端的にわかるので、前述の『土くれ』の一シーンを引用してみよう。
1 土/土、と言う時、ひとは何を想い出すだろう。/掌にすくいとった、土の感触。/ザラザラした、あたたかさ。/ふみ固められた、三和土。/なだらかな丸みをもった、丘。/耕された、大地。/日照りのあとのひび割れ。/……。/……。/そのすべてを、私たちは木内克のテラコッタの中に見つける事が出来る。/それはまず、何よりもまず、地球そのものだ。/木内克のテラコッタの中にかくされた大地の風景。/大地の風景は、次第にうねりを増す。/創世記の最初の夏のように、/大地はふくらみ、くぼみ、/光を微妙なひだの中にたたえ、/赤い輝きを増してゆく。/そして遂に、母なる大地は姿を現す。/豊かな腹を想わせる 丘。/腰を想わせる 山。/母を想わせる 太陽。/太陽を想わせる 顔。
『ドキュメンタリーを創る』より
一篇の詩のようではないか!
私が就いた《かぶきの音》(1991年)は歌舞伎の音楽や効果音などを描いたものだが、そのシナリオの一シーンは次のように書かれていた。
大江戸の空(東京の空ではない)
名カメラマンの瀬川順一さんもさすがに何を撮るか頭を抱え、結局このシーンは撮影されなかった。
撮影現場での松川さんは、「カメラマンが自らいいと思って撮ったものでない限り、いいカットではない」とうそぶきながら、ほとんど何も言わなかった。ただ、絶対に嫌うことが二つあった。一つは撮影対象に対して、撮影の都合で待ったをかけたり、故意に同じことをやってもらうことである。《鳥獣戯画》のナレーションに「とりかえしのつかぬ墨の痕」とあるように、私たちは常に一回性を生きているのだということを思い起こさせた。二つ目は、野辺の花を撮る時などに、実際に吹く風を待たずに、扇いで風を作って撮ったり、樹を揺らしたりした場合である。二つともそうであるが、現実にあるものに対しての「演出」を嫌った。松川さんは常々言っていた。「ドキュメンタリーは、一カット一カットは全部事実。その事実でつくるから面白いんだよ。最初からつくるんだったら、劇映画をつくればいい」と。
そして、何と言っても一番ユニークなのは編集だろう。今や隔世の感があるが、私が関わった時期もまだフィルムで撮られたものが多かった。以下に書く編集方法もフィルムでの編集の話である。松川さんの映画はビュワー(フィルムを見る機材、編集する時に使う)で生まれると言っても過言ではない。そのための入念な準備は、B4サイズのスケッチブック全てのページを八分割することから始まる。その一つ一つハガキ大の大きさに画コンテを描いていくのである。なぜ編集で画コンテ?と思われる方が大半だろう。通常画コンテを描く場合は撮影のために描くものだからである。しかし松川さんの場合は逆で、撮影したものを一カットずつ画に描き起こしていくのである。そしてスケッチブック全ページをコピーし、ハサミとセロテープで切り貼りして壁に貼っていく。画コンテを並べながら、ああだこうだと構成を考えるのである。構成がまとまると、並べられた画コンテの順番にフィルムを繋いでいく。明らかな撮影技術上のミス以外「ドキュメンタリーにNGはない」というのが原則なので、一回目に繋ぐのは全撮影分になる。「人の顔を描く時にね、最初から目だけを丁寧に描いていくとうまくいかないんだよ。大きく捉えてから細部に手を入れないとね」と言い、その言葉通り、カットを短くしていく作業(カットポジを出すと呼ばれる)は一番最後に行われた。繋いだフィルムを映写機にかけて見て、画コンテで編集を考え、切り貼りする。この繰り返しの中で、不思議と必要のないカットが見つかり、それぞれのカットがあたかも定位置のように収まっていく。
しかし、なぜここまで面倒な方法を取るのだろうか? 松川さんは画家を目指していた方で、手を動かすことが好きだった。フィルムも物としてあるので、切ったり貼ったりも手作業であり、そのこと自体を楽しんでいたことは間違いない。だが、好んでよく口にした例え、ロートレアモン伯爵の《マルドロールの歌》の有名な一節「ミシンとコウモリ傘との、解剖台のうえでの偶然の出合い」のような、頭だけで考えたのでは思いもよらない繋ぎが見つかるというのだ。一方で構成に関しては「起承転結」を頑なに貫いた。上手くいっていない時は、「起」がなかったり、「承」がいくつもあったりするものなのだと。編集が終わりに近づくと、「今、最高のスープが出来上がるところなんだよ。時間をかけてつくったね。その最高のスープにね、小指のほんの先っぽくらいの糞が入ってもスープは台無しになってしまう。最後まで細心の注意が必要なんだ」と話した。
このような時間を松川さんと過ごした。「チャンスの女神にはね、後ろ髪はないんだって。だからチャンスを逃すと捕まえられないんだよ。チャンスの女神の前髪をつかまないとね」と、松川さんは私に何度も話してくれた。「チャンスの女神に後ろ髪はない」という松川さんが好んだ言葉は、私たちは誰しも「とりかえしのつかぬ」一回性の生を生きているということを常に思い起こさせる。
(ひゅうがじ たろう/映画監督)
田中 晋平
付記:本稿は、『国立国際美術館ニュース』244号掲載の拙稿「アルチザンのまなざし—中之島映像劇場について⑧—」に加筆・修正を行い、再録したものである。
《不安な質問》という映画をご存じだろうか。1970年代、食品の安全に疑問を抱いていた都会に住む人々が「たまごの会」というグループを結成。メンバーで田舎に土地を購入し、養鶏の小屋を建て、野菜を育てていき、豚まで飼いはじめる、こうした活動を会の内側から捉えたドキュメンタリーである[1]。自主農場の生産物は、都会の団地で暮らす人々のもとへ配送され、団地では食べ残しのゴミなどを回収、豚の餌として活用される。豚の全身を主婦たちが調理して、食卓に並べて舌鼓を打つ姿など、五感を刺激してくる場面も多い。40年前の映画だが、グローバルな食料供給のネットワークやその品質の問題、膨大なフードロスのようなシステムの歪みに直面する現在のわれわれにも問いを投げかける作品である。
しかし、《不安な質問》の魅力はそれだけではない。記録された自主農場の活動を、1970年代の日本という時代や場所に縛られない営みとして想像力をめぐらせるための演出が、映画に散りばめられているのだ。たとえば、後半の農場全体(あたかも砦のような様相を呈しているのだが)を捉えたロングショットを見よう。農場の屋根の上にのぼってカメラに手を振り、赤い旗をなびかせる人々が映し出されるこの場面は、セルゲイ・エイゼンシュテインの《戦艦ポチョムキン》(1925年)の結末部、海上で合流した軍艦が祝福をし合うシーンを模したものだとされる[2]。映画史の記憶を喚起するイメージだけでなく、ピーテル・ブリューゲルの描いた《農民の踊り》(1568年頃)を画面に繰り返し登場させるなど、《不安な質問》は、「たまごの会」の活動を、別の時代や土地で生きた民衆の闘い、祝祭の記憶と接続しようとしている。
《不安な質問》を演出した映像作家は、松川八洲雄(1931-2006)。東京大学文学部美学美術史学科で仲間だった松本俊夫、藤原智子らとともに、1950年代後半に記録映画の世界に身を投じた人物である。新理研映画社、日映科学を経てフリーとなり、数多くのPR映画や産業映画を演出、《鳥獣戯画》(19などのアート・ドキュメンタリーの先駆というべき傑作も発表した。自らを「映像のアルチザン」と呼ぶ松川は、多種多様なテーマや素材・事実を映像作品に結実させ、通常のドキュメンタリーの手法を踏み越えるような表現も生み出していくことで、国内外で高い評価を得た。そして、PR映画の場合でも《不安な質問》のような自主製作作品でも、このアルチザンのまなざしは、現実の襞に分け入って、その奥底に流れる異質な時空間を浮彫にしていく。
松川の手がけた作品は、「今」と「昔」の空間が隣り合い、干渉し、異化する様子に立ち会っているような映画経験をもたらしてくれる。たとえば、初期の代表作で実験的要素が詰め込まれた《鳥獣戯画》は、12-13世紀に描かれた絵の世界と、それを撮影している現在の空間とを「立体派のオブジェのように」組み合わせた映画だと述べられている[3]。1944年の落雷で失われた法輪寺の三重塔の再建を記録した《飛鳥を造る》も、物理的な建造作業のプロセスを追うだけでなく、数百年間不変の存在として塔が建ち、人々の生活の風景のなかにあった記憶自体を甦らせようとする。《ムカシが来た—横浜市長屋門公園古民家復元の記録—》、あるいは《民俗芸能の心琵琶湖・長浜 曳山まつり》などの場合、過去の民俗や伝統芸能を記録しながら、そこに参加する子共たちの生き生きした姿が重ね合わされていて、郷愁を誘うのとは違う、瑞々しさを得た作品群になっている。そして、敗戦後に占領軍に没収されていた原爆投下から一ヶ月後の広島の街と人間を記録したフィルムに、製作当時の広島の映像を加えて構成された《ヒロシマ・原爆の記録》では、残された災厄の記憶を現在においていかに再構成すべきかが問い直されている。松川が、ギリシア現代史を神話世界のように描き、異なる時代をワンショット内で自在に行き来してみせた、テオ・アンゲロプロス《旅芸人の記録》(1974-75年)を賞賛していたのも、上記のような自らのドキュメンタリー創りとの接点を見据えていたためだろう[4]。
《不安な質問》でも、農場建設のために地面を掘っていると、1500年前頃の土器が発掘されるというハプニングが起きるのだが、松川はその出来事に強い関心を向けている。自主農場のドキュメンタリーという目的からはズレているようにもみえかねない場面のようでいて、この土器の存在が、食物の問題と向き合う人々の映画の渦中に、異なる時代の人間たちが何を胃袋におさめ、生活を営んだのかを想像できる余地を提供してくれているように思われる。《戦艦ポチョムキン》やブリューゲルの絵が示していたように、松川は「たまごの会」の活動を追いかけながら、ここではない別の時間、異なる空間の記憶を土器のなかに感知して、映画内にさりげなく配置しているのだ。

《不安な質問》制作風景 提供:国立映画アーカイブ
《不安な質問》には、当初《ユートピア斗争宣言》という仮タイトルが与えられていた。「たまごの会」の活動を記録しながら松川は、存在しないはずのユートピアの可能性を想像していったのだという[5]。ただ、松川がそこに垣間見た空間は、ユートピアというより、ミシェル・フーコーが唱えた、「ヘテロトピア(heterotopia)」と呼ぶべきものだったかもしれない。異種混淆的な空間とされる「ヘテロトピア」には、いくつもの規則があり、たとえば「ふつうは相容れず、相容れるはずもないような複数の空間を一つの場所に並置するという規則を持つ」とされ、また「すべての時間からなる一つの空間」[6]といった表現もなされる。具体的には墓地や植民地、あるいは博物館・美術館、さらに庭園、舞台や映画館などの事例をフーコーはあげていく。松川の視線は、常にこうした異なる空間や時間が並置されるヘテロトピアを、撮影された無数の素材から探し当てようとしてきたのではないか。あるいは、このアルチザンのまなざしが現実を穿ち、スクリーンに異質な時空間を立ち現れさせるのだと考えた方が正確かもしれない。遡れば、松川と岩佐寿弥が脚本に参加した黒木和雄監督の《とべない沈黙》(1966年)も、北海道に生息しないはずの蝶と少年が出会う、空間的想像力の飛翔の映画であり、既にそのまなざしが宿されていた。
人間国宝から無名の労働者たちまで松川の映画には登場するが、彼らの労働が現在の社会にとっていかに有用かを映画で知らせるのではなく、熟練された身振りの背後に堆積した過去の時間を、観る者に感受させる。《ヒロシマ・原爆の記録》のように、その時間の重層性を示す演出は、無数の死者たちの声やイメージを映画の内側に確保することにも通じている。さらに松川の手がけた映画に躍動をもたらす子供たちの姿も、「今」という時間や空間を異化する存在として忘れるべきではない。《不安な質問》でも、作業する大人や動物に混じって、農場を駆け回る子供らの姿が、映画に大きな開放感を与えてくれている。食物の問題からわれわれの生の条件を問い直す《不安な質問》は、「たまご」が新しい命の形象であるように、この子供たちの未来に祝福を贈る映画でもあるだろう。エンドクレジットの後、カメラマンの瀬川順一が粘って撮影に成功したという、鶏が卵を産む瞬間がスクリーンいっぱいに映し出されるのだが、松川は次のように書いている。「この最後の卵は永遠にくり返される“希望”に他ならない」[7]。
2022年3月12日、13日に開催する第22回中之島映像劇場では、映像のアルチザン・松川八洲雄の仕事を回顧する。
註
(たなか しんぺい/国立国際美術館客員研究員)
第22 回中之島映像劇場
映像のアルチザン―松川八洲雄の仕事― 配布資料をウェブに再掲
編集
田中晋平(国立国際美術館客員研究員)
編集補助
武本彩子(同研究補佐員)
執筆
森田のり子
まつかわゆま
日向寺太郎
田中晋平
発行
国立国際美術館
530-0005
大阪市北区中之島4-2-55
06-6447-4680(代)
https://www.nmao.go.jp
発行日
2022 年3 月12 日