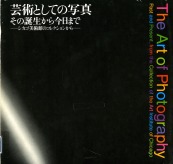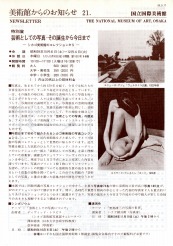会期:1984年10月6日~12月4日
写真が発明されたのは19世紀前半のことだが、今日ではそれは新しい芸術表現のメディアとしての位置を確立するにいたっている。本展は、シカゴ美術館の協力を得て、写真が初期の実験段階を経て、写真固有の表現上の特質と芸術的価値に対する自覚と一般の理解のもとに、写真が自らの地位を確立するにいたった歴史を展望するために企画された。
総数180点におよぶ出品作品はすべてシカゴ美術館の所蔵あるいは寄託品から選ばれた。シカゴ美術館が写真を収集し始めたのは1949年からであるが、その収集のポイントは芸術としての写真作品においており、上記のような展望展にはもっともふさわしいものといえよう。
全体の構成は次のように17章に分けた。
1.きわめて独自な芸術
2.第一の世代
3.ナダールとキャメロン
4.遠いものを身近かに
5.アジェとフレデリック・エヴァンズ
6.美的意識
7.スティーグリッツとスタイケン
8.写真の純粋性
9.マン・レイとモホリ=ナジ
10.時間と運動性
11.ルイス・ハインとウォーカー・エヴァンズ
12.デザインの優美さ
13.ユージン・スミスとロバート・フランク
14.スタジオの照明から
15.ポーターとマイナー・ホワイト
16.予期せぬことへの期待
17.写真の枠をこえて
ひとつおきの章に代表的な写真家2名の章を設けることによって、芸術写真全体の歴史をたどりながら、同時にすぐれた写真家の作品もまとめてみせるという構成であった。写真家数は全部で74人だが、うち14人によってこれらの章が構成されていた。
シカゴ美術館のコレクションの発端はアルフレッド・スティーグリッツのコレクションを未亡人ジョージア・オキーフから寄贈されたことに始まる。その後 1970年代になってジュリアン・リーヴィ・コレクションの大部分が入り、この二つのコレクションの性格、つまりオリジナル・プリントによる芸術としての写真の収集という特徴をつくりあげたのである。本展はこの中から輸送に耐える作品180点が選ばれたのだが、その中には日本のすぐれた写真家野島康三、シカゴに学び、アメリカで活躍し、現在は日本に戻った石元泰博が含まれている。
概説を書いているシカゴ美術館写真部門キュレーターのトラヴィスによれば写真(芸術)は光と時間と対象の3つの要素を扱う芸術であり、そのなかでも光を最高の要素とする芸術だというが、本展は日本においてもあらためて写真の芸術問題に話題をなげかけたといえよう。
会場は4階、3階、2階を使用した。