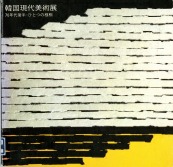会期:1983年8月20日~9月25日
民芸、民画、陶器など、韓国の伝統的な美術、工芸には深い関心が寄せられているが、今日の美術の状況については、日本ではこれまで意外に知られていなかったといえる。本展は国際的な活躍を見せる1920年代、30年代生まれの作家から、50年代生まれの若い世代まで、39作家(平面29名、立体10名)の98点によって、はじめて本格的に紹介しようとしたものである。
韓国美術に顕著な特色としてよく指摘されるのは、絵画におけるモノクロームの表現の重厚さであり、また立体、平面を問わず、マチエールをとらえる感覚の繊細さである。本展の会場でも、まず印象づけられたのは、大作のタブローを中心にした、そうした作品群のかもしだす、静謐な存在感であった。
平面作品は、大きく見て二つの傾向に分かれていた。一つは主に白によるモノクロームの作品であって、30年代生まれの朴栖甫(パク・ソーボ)や鄭相和 (チョン・サンホア)ら、エコール・ド・ソウルと呼ばれている作家を中心とする。この傾向は、70年前後の国際的なミニマリズムの絵画に呼応するものであると同時に、また白一色の画面のディテールの深まりに、韓国の感性の伝統をも強く感じさせるものでもあった。もう一つは70年代の後半にあらわれた具象的なイメージを取り戻したドローイング風の作品であり、安炳奭(アン・ビョンソック)ら、若い世代の仕事に共通した傾向である。
立体作品では、木やテラコッタ、石、鉄などの素材感を素直に生かした造形が多く、また、日本と同様に、大規模なインスタレーションの仕事が台頭していることも興味深かった。ビデオの映像と自然石を組み合わせた作品(朴■基(パク・ヒョンギ))なども出品されており、韓国美術の思わぬ多様性を垣間見せてはいたが、総じては、西欧的な個性の主張といかにも対極的な、静かな思索と禁欲性を強く感じさせる世界であったように思う。
会場は、3階、2階、および1階Aの展示室を用い、ほぼ上記の傾向別に応じた陳列を試みた。
なお、本展は1981年にソウルで開かれた日本現代美術展の交換展として企画されたものである。作品選定とカタログ作成には、韓国側の美術館員、批評家、美術史家などからなる7名の委員が当り、当館をはじめ、東京都美術館、栃木県立美術館、北海道立近代美術館、福岡市美術館の5館を巡回した。
※「朴■基」の「■」は、火へんに玄