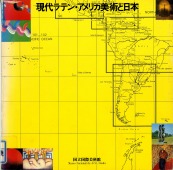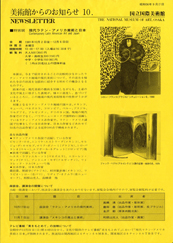会期:1981年10月2日~12月6日
本展は、これまでわが国で紹介されることの少なかったラテン・アメリカの国々の現代美術について、その活力を秘めた今日の状況を包括的に紹介しようとする意図のもとに企画された。
出品は、アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、キューバ、メキシコ、ペルー、ウルグアイ、ベネズエラの9ヵ国の作家に同地域に関係ある日本人作家を加えた51作家の作品100点であった。
ラテン・アメリカの国々は、各国の持つ歴史的背景、所属する言語圏の違いなどの諸要素が絡みあい、その現代美術の表現に微妙な差異がみられたが、また、共通する傾向も現われていた。それは、ヨーロッパや北アメリカの美術への志向や、広大な自然環境や、土着的な文化を背景にしたものなどを混在させながら、ラテン・アメリカ美術の独自の方向を探っているように思われる。リオデジャネイロ在住の美術評論家、マルク・ベルコウィッツが本展カタログに記しているように、われわれは、ヨーロッパや北アメリカの美術に適用されている方式や原則によってではなく、「みずからの身元をさがし求めている美術」として現代ラテン・アメリカの美術をとらえる必要がある。このように、土着の文化とヨーロッパの文化が混血する独特の文化や広大な風土を背景にするラテン・アメリカの現代美術は、二ューヨークやパリの洗練された感性や理知的な美術とはかなり異った骨太さや土俗的なたくましさを内包しているように思われた。
出品国は9ヵ国であり、これはこの地域の主だった国にすぎないし、チリのマッタ、ベネズエラのソトのようにヨーロッパを舞台に名を知られる作家だけで代表される国も含まれていたが、はじめてといってよいこの種の展覧会ということもありダイジェスト的にならざるをえなかった。それでも、会場には各国の特徴が十分でるように展示効果に配慮した。
会場は4階、3階、2階を使用し、ブラジル関係作家21名の作品42点を3階に、メキシコ関係作家11名の作品22点を2階に展示した。また4階には、アルゼンチンの作家10名の作品19点、チリの作家1名の作品2点、コロンビアの作家2名の作品3点、キューバの作家2名の作品4点、ペルーの作家2名の作品4点、ウルグアイの作家1名の作品2点、ベネズエラの作家1名の作品2点をそれぞれ国別に展示した。
メキシコのマヌエル・フェルゲーレス、ビセンテ・ロホの作品には、アステカやマヤの痕跡が色濃くただよい、エンリケ・エストラーダの作品からは熱っぽく激しい人間性が伝わってきた。ブラジルの場合、アルカンジェロ・イアネリやアントニオ・ディアスの幾何学的な構成と渋い色調の作品や、豊田豊、大竹富江、楠野友繁、間部学、リディア・オクラムらの日本人作家および日系作家の作品も興味をひいた。また、アルゼンチンの作家でパリに住むアントニオ・セギ、フリオ・ル・パルク、ルイス・トマセージョの作品と、ニューヨークに住むマルセロ・ボネバルディやレオポルド・マレールの作品との対比が明確にでていたのが印象的であった。キューバ出身のアギュスティン・カルデナスの彫刻は、アフリカの原初的生命感が凝縮しているかのようであった。