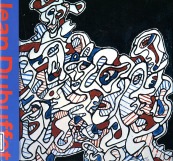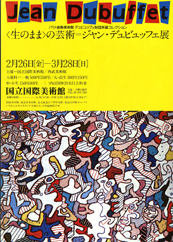会期:1982年 2月26日~3月28日
本展はパリの装飾美術館とデュビュッフェ財団のコレクションを中心に、163点の作品で画家の軌跡を辿るものであった。デュビュッフェはアンフォルメル運動の先駆的存在として、またアール・ブリュト(生のままの芸術)の提唱者として、国際的に大きな影響を与えてきたが、日本で本格的な紹介がなされるのは、これがはじめてであった。出品作品は油彩やアクリルのタブローが、1943年の《街路》から1981年の《5人の人物のいる光景》まで45点、デッサンやグワッシュ、型押しのアッサンブラージュなどが117点、他に彫刻が1点(《ロゴスへの里程標Ⅲ》1966年)であった。
1940年代の出品作品は、線描を主体にした童画風のイメージのものが多く見られ、また油彩では絵具が素材としての物質感を強く示すまでに厚塗りされている。サハラへのたびたびの旅行を反映して、砂漠の光景に取材したグワッシュも多い。
1950年代の最初に制作された《ご婦人の身体》の連作からは、油彩や水彩が4点出品された。油彩の《髪を結う女》(1950年)は、砂などが混入され、グロテスクな裸婦がむしろ鉱物的な絵肌で描き込まれている。この異物の混入は続く《土壌と地面》シリーズや1960年の《土の果物》などのタブローで、さらに方法として徹底されて行く。
1960年代から70年代前半にかけての出品作品の中心は、強い輪郭線で囲いとられた地図のような模様で画面を埋める《ウーループ》と呼ばれる仕事であり、この時期には色彩はしだいに明快に整理されて行き、画材もビニール塗料やマーカーペン等が用いられて、グラフィカルな効果を強めるようになる。モニュメント彫刻や庭園などの大規模な作品も、70年前後に試みられているが、本展では、《ヴィラ・ファルバラ》などが5点の大きな写真パネルによって紹介された。
展示会場は3階と2階を使用し、年代順を原則としながらも、タブロー、デッサン、アッサンブラージュなどに分け、また画題ごとのまとまりをも考慮した。また、2階会場ではビデオ「ジャン・デュビュッフェのアトリエ訪問」(彫刻の森美術館制作、1975年、上映時間約50分)を常時放映した。
なお本展は、当館に先立って西武美術館で1月2日−2月21日に開催された。