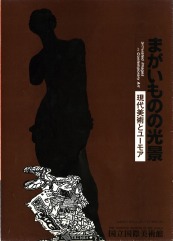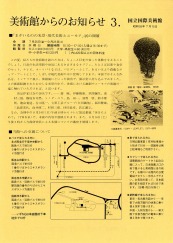会期:1980年7月25日~9月23日
日常の卑近な生活空間や、そこに登場するさまざまなオブジェとのかかわりの直截さは、戦後の美術の大きな特徴の一つとなっている。本展は写真やイミテーション、トロンプルイユ、あるいは既製品や廃品の転用などの方法によって、まがいものとしてそっくり価値転換されてしまった日常の光景という視点から、そのような現代美術の一断面をアクチュアルに示そうとしたものであった。また多くの出品作品がパロディーとしての側面を持つことから、美術における風刺やユーモアの今日的な意味に照明を当てることも、企画の意図の一つであった。
たとえば、既製品をそのまま作品化することは、ダダイスムからシュルレアリスムを経て、戦後のホップ・アートにいたる、いわゆるオブジェの思想を背景にしているが、それは美術において神聖視されてきたオリジナリティーの概念を危くするとともに、また反面、われわれを取りまく物資文化へのアイロニカルな批評ともなっている。生活の中で合目的的とされていた形態も、いったん日常の文脈から異化されると、奇怪なあるいはユーモラスな物体としての表情を顕わにしはじめるのである。
本展に出品された、さまざまな生活のオブジェも、いずれもそのように視覚的に強く異化されたものであった。鉢植えの木をたんねんに刈り込んでつくった巨大な盆栽の電球(須賀啓)。鋭いトゲで触覚を逆なでするアルミのテーブルウェア(伊藤隆康)。薄い陶板に刷られたケバケバしいバーゲンのちらし(三島喜美代)。あるいは団欒の場であるべき応接セットが銀色の突起物でびっしりと埋めつくされ(草間弥生)、中型乗用車が不明の記号でおおわれ(向井修二)、オルガンは野戦の迷彩色で色どられる(谷川晃一)。そのような光景は、都会の平穏な生活者であるわれわれの想像力を挑発し、時に不安におとしいれるものといえるかもしれない。
出品作品は、ポップ・アート的なものを中心に、ハイパー・リアリズムから観念的な傾向のものまで、多岐にわたるが、会場ではそれらを、いずれも一つの生活空間としてのまとまりの中に(たとえば室内風に、街頭風にといった演出で)展示することを試みた。結果としては、やや遊びの要素が強く出すぎたきらいがあり、方向性をもった展示の演出と、個々の作品のコンセプトとのかねあいを見定めることは、今後の課題として残されたといえる。
出品作家は、上記の他に、靉嘔、重村三雄、シノダ・ユウ、篠原有司男、島州一、鈴木慶則、建畠覚造、七彩工芸グループ(欠田誠ほか)、福田繁雄、村岡三郎、持田総章、若江漢字の18名。総出品点数は61点。