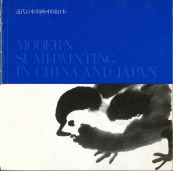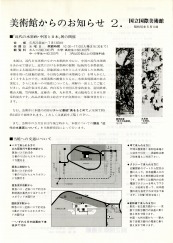会期:1980年5月23日~7月13日
この展覧会は、近代日本美術の水墨画を中心に、中国の近代水墨画をあわせて展示し、近代における水墨画の展開を明らかにようとするものであった。
中国の唐代におこった水墨画は、わが国に中世の末期にもたらされ、大和絵と交流して、絵画の重要なジャンルとして展開し、さらに、近世には南画的水墨画の発生をみるにいたった。近代になり、横山大観、川端龍子、横山操、東山魁夷などの秀れた作家たちによって、伝統的な大和絵的水墨画の近代化が推し進められた。大観は、従来の大和絵的水墨画の伝統をふまえながら、片ぼかしをはじめとする水墨画の技法的な革新をおこない、水墨画に立体感とリズム感を与えることに成功した。また、西洋の写実画法である遠近法を水墨画に導入した作品もあらわれてきた。竹内栖鳳の《ベニスの月》(1904年)、山元春挙の《雪松図》(1908年)、川合玉堂の《二日月》(1907年)などは、東洋占来の水墨画の形式に、西洋の写実主義を反映した画期的な水墨画であった。
近代の西洋絵画史上、印象派は光の表現に新生面を開いたが、この印象派流の光のとらえ方を水墨画にとりいれたのが近藤浩一路であった。浩一路は、空疎な精神主義に陥っていた水墨画に、近代的な感性を込めて、自然の風物を分析し、その光景を墨一色の微妙な諧調によって表現し、《雨余晩駅》(1929年)、《広沢雨余》(1934年)などの作品を発表した。
戦後、抽象美術は、国際的にさかんになったが、その影響をうけて、日本の水墨画の世界にも抽象表現を試みる作家が登場してきた。本展では、抽象表現的な水墨のひろまりに、無機的な直線を描き、無限の空間を感じさせる山口正城の《遠ざかるもの》(1959年)、水芭蕉のイメージから抽象的な幾何学的形態を追求しつづける佐藤多持の《水芭蕉曼陀羅(黄21)》(1970年)などによって、そのことを跡づけた。
一方、書の分野では本来の特性である文字性を脱却した、いわば、抽象的水墨画ともいえる墨象の世界をきりひらいた井上有一の《骨》(1959年)、森田子龍の《坐俎上》(1958年)を展示して、新たな墨の世界の方向性を示した。 以上のような造形上の問題に対して、画題の問題にも変化があらわれてきた。丸木位里、俊の《原爆の図》は、水墨によるデッサン風の写実表現で、今日的な社会問題をとりあげた異色の大作であった。
社会主義の現代中国では、このような造形上の問題や画題に対する問題意識のあらわれ方は、わが国よりも穏健で、張大千の《水仙図》(1953年)、傅抱石の《後赤壁図》(1964年)、呉作人の《金魚図》(1978年)、宗其香の《山水図》(1978年)のように、文人的な趣味の域にとどまった作品が多かった。しかし、李行簡の《毛主席旧居図》や盧沈の《塞上秋色図》(1978年)のように、毛思想の顕彰や少数民族の風俗をあつかった作品もみられ興味をひいた。
会場は4階、3階を使用し、展示替えを含めて、日本人作家29名の65点と中国人作家34名の79点を展示した。