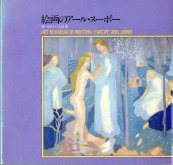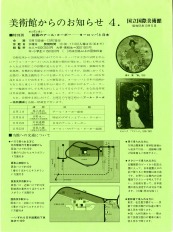会期:1980年10月10日~12月7日
19世紀の末から20世紀の初めにかけての、世紀のかわり目におけるヨーロッパと日本の絵画に焦点をあわせ、そこに、精神的かつ造形的な面で「新しい美術 (アール・ヌーボーという語の本意)」を創り出そうとする共通の性格を認めようというのが、本展のねらいとするところであった。特に、本展ではモチーフを「女と花と夜」にしぼり、この時期のヨーロッパと日本の絵画約150点で構成された。
浮世絵版画を中心とする日本美術の影響で、19世紀後半の西欧美術には、日本趣味(ジャポネズリ)といわれる流行が生まれるが、それは単に主題やモチーフについて見られるというだけではなく、画面構成や色面処理の方法などといった造形上の問題にまで及んでいた。
こうした日本趣味の流行を受けて、1890年代の半ばから1910年頃にかけて、工芸やグラフィック・デザイン、建築の分野を中心に、全欧的な規模で展開したのが、いわゆるアール・ヌーボーである。様式的には、有機的な曲線の多用とか、大胆な平面構成などが特徴としてあげられる。
一方、この時期のヨーロッパ絵画についてみてみると、各国に個性的で多様な表現があらわれてきた時期であったと言うことができよう。従って、これより前の印象派とか、後の表現主義の絵画の場合とは違って、必らずしもこれらが、ひとつの傾向として大きく捉えられることは、従来あまりなかったようである。しかし、こうした多様な絵画表現の中にも、輪郭線の多用とか平面性の強調とか病的な色彩感覚などといった、アール・ヌーボー独特の造形的特徴を有し、しかも装飾的、象徴的、唯美的な表現内容を共通項として認めることのできるような作品が、数多く見られることから、これらの絵画を、「新しい美術(この場合は絵画)」として捉え直そうという考え方が、近年あらたに生まれている。
ところで、黒田清輝や浅井忠らの紹介で、日本にアール・ヌーボーがもたらされたのは、1900年頃のことで、ほぼヨーロッパと同時代的であったと言えよう。しかし、その他多くの美術思潮も同時に流れ込んできたため、日本におけるアール・ヌーボーは、今まであまり注目されることがなく、西欧における場合と同様に、工芸やグラフィック・デザインの分野で指摘されるぐらいであった。しかし、この時期の日本の洋画や日本画にも、実は、アール・ヌーボーの影響が及んでいたことも確かで、世紀末的な雰囲気の反映は、広くこの時代の絵画にうかがえるところである。ただ、ヨーロッパ絵画の場合のような、造形的にはっきりした特徴が指摘できるというわけではなかった。
以上のような視点から企画された本展では、「アール・ヌーボーの絵画」を最初に描いた画家といわれるベルナールをはじめ、ドニ、ボナール、ランソン、ヴァロットン、ヴュィヤールなどナビ派の作家の他、彼らに影響を与えたといわれるルドン、ノルウェーの表現主義の作家ムンク、ウィーンの装飾画家クリムトらの作品をとりあげた。また、これまであまり日本に紹介されることのなかったオランダの画家、トーロップやトルン=プリッカーの線描主体の神秘的な作品を加えたり、アマン・ジャン、カリエール、ル・シダネルやコランといったサロン画家たちの作品や、ピサロやベックリンの作品も併せて展示した理由は、こうした傾向が、ヨーロッパ全土にわたる同時代的な精神による所産であると考えられたからである。
また、日本における「アール・ヌーボーの絵画」として、洋画では、藤島武二、青木繁、黒田清輝、岡田三郎助ら白馬会系の作家や、満谷国四郎、中村不折ら太平洋画会系の作家の他、斎藤与里、小杉未醒、大久保作次郎、田中保、竹久夢二らの作品をとりあげた。また、日本画では、鏑木清方や松岡映丘、村上華岳、土田麦僊らの他、今まであまりこうした関連の中で考えられることのなかった岡本神草や甲斐荘楠音らの作品まで幅広くとりあげた。橋口五葉、伊東深水、田中恭吉、恩地孝四郎、永瀬義郎らの版画も加え、荻原守衛と佐藤朝山の彫刻をとりあげたのも、日本におけるアール・ヌーボーの影響が全面的なものであったことを物語る例としてであった。