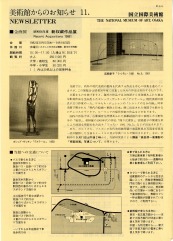会期:1982年8月5日~9月19日
本展は、内外の現代美術を中心に作品の収集を進めている当館が、昭和56年度に購入、寄贈などで収蔵した作品を一堂に集めて紹介するために行ったもので、3階と2階の展示室及び1階屋外展示場に22作家、54点の作品が展示された。
出品作品のうち、海外の作品では、立体派から生命感あふれる独自な彫刻作品を生み出したオシップ・ザッキンの《デメテール》(1958年)、現代美術の原点に立つ作家の一人であるマルセル・デュシャンの《カバンの中の箱》(1936−41)、わが国では余り知られていないチェコスロヴァキアのミラン・グリガルの《線の譜表》(1977年)やルーマニアのソーリン・ドゥミトレスクの《詩人ダニエル・トゥルチェアのための第1の素描》(1979年)などを展示した。一方、国内の作品では、心象風景を抒情あふれる抽象絵画のなかに表現した小野木学の《風景》(1975年)、若林奮の1960年代を集約した作品《残り元素Ⅳ》(1966年)、宮脇愛子の簡潔な形により清々しい空間を生み出した《うつろい1981 No.5》(1981年)などを展示した。
なお、当館では、オリジナルな作品に加えて美術作品の複製資料も収集しているが、56年度は写真家の奈良原一高に依頼して撮影した《南蛮屏風》(六曲一双)の原板をもとに、ほぼ原寸に近い全図写真パネル2点と20点の部分拡大写真パネルを作製した。この《南蛮屏風》は、故池長猛氏(神戸)のもとから戦争直後、在日ポルトガル大使館を経てポルトガルのリスボン国立博物館の所有となったもので、我が国では一般には見ることが出来なかったが、このたび初めてその全容が紹介されたといえる。また、拡大されたその部分写真には、画面の特徴的なイメージが、写真家・奈良原一高の眼によって鮮明にとらえられ、見すごしがちな細部の迫力を現代によみがえらせた。
また、当館は現代美術の発展および広報普及の一環として各種美術展覧会、コンクールにおいて、国立国際美術館賞を授与しているが、本展では次のような5 つの国立国際美術館賞受賞作品を紹介した。古井洵《円の隆起(ロ)》(第15回現代日本美術展 1981年)、岡本敦生《かたむいた球体》(第9回現代日本彫刻展 1981年)、田中薫《ななめに積んだn個の正方形》(第2回ジャパン・エンバ美術コンクール 1980年)、金沢健一《接合体1》(第3回ジャパン・エンバ美術コンクール 1981年)、前川強《よこ》(第4回ジャパン・エンバ美術コンクール 1982年)。