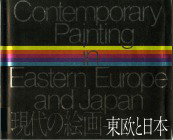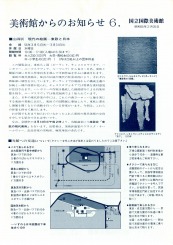会期:1981年 3月5日~3月31日
この展覧会はポーランド、チェコスロヴァキア、ハンガリー、ユーゴスラヴィア、ルーマニアの東欧五ヶ国から計23名の作家による作品85点と、東欧に関係した日本人作家14名による54点の作品により構成された。出品作品は展覧会規模が限定されたため平面作品に限られたが、東京国際版画ビエンナーレなどを通して以外、あまり知られていなかった東欧の現代美術がわが国で初めて全般的に紹介される機会となった。
東欧の美術は今世紀に入ってヨーロッパの美術に新鮮な活力を与える役割を果たしており、ロシアと並んで前衛運動に寄与した作家は数多い。中でもルーマニアの彫刻家C・ブランクーシ、同国出身でダダ運動の創始者T・ツァラ、近代デザイン運動を主導したハンガリーのL・モホリ=ナギなどはよく知られている。またボーランドでは構成主義の重要な運動がある。そして社会主義国家として出社会的な役割、一般大衆との関係といったイデオロギーを踏まえた基本的問題から検討が加えられてきた。ポーランドやユーゴスラヴィアにおけるグラフィック・アートの隆盛はその成果の表われの一つであり、各地の版画ビエンナーレには日本からの出品も数多い。
展覧会は各国一名づつの美術評論家の協力のもとに作家ならびに作品の選定を行い、それらのオーガナイザーに自国の現代美術紹介を兼ねたカタログ論文を依頼した。作家選定は、各国ごとに一つの視点を持って行われ、各国の現代美術の総花的な紹介ではなく、一国のセクションにおいて出品作品が一つのまとまりを持ち得るような方向で行われた。また、会場における展示は各国ごとのセクションに分けて行われた。
ポーランドの6名の出品作家は、戦前の構成主義の伝統を反映するが、グラフィックな処理や淡白な色彩などに見られる清新な詩情が全体に共通するところであった。
4名の作家によるチェコスロヴァキアの作品は、素材を生かしたレリーフ的なものが多く選ばれ、中にはむしろ立体作家として知られる作家も含まれた。素材の物質性に対する強い執着は同国の美術一般に見られる特質である。
ハンガリーは具象的な作品に限られ、4名の作品はすべて版画であった。それらは、細密な描写による形象が画面を満たし、バロックやシュルレアリスムとの関係を思わせた。西欧と最も活発な交流を持つユーゴスラヴィアは、6名の版画作家による作品が選ばれた。この国は上述の国々と異り複雑な構成の多民族国家であり、また一部にギリシア正教とビザンツ文化の伝統を持つ地域を含んでいるが、出品作品は中でも活発な中心地であるリュブリアナの作家を中心として選ばれた。
ルーマニアからの3名の作家による素描と版画の作品は、ビザンツの東方的神秘主義やイコンを思わせる象徴的な性格によって独特の傾向を見せ、わが国では現代美術に関して全く未知の国であっただけに、これらの作品は注目された。
日本人作家のセクションには、クラコウやリュブリアナの国際版画ビエンナーレでの受賞者をはじめ、東欧各地での個展開催やシンポジウムへの参加によって同地の作家達との交流の深い作家など14名の作品が出品された。またポーランドのウッジで開かれた1979年のジャパン・アート・フェスティバルでの受賞者がこれに加えられた。東欧との交流は日が浅く、関係作家も比較的少ないが、それだけ一部の作家における関わり方には深いものがある。全体の特色としては、版画ビエンナーレなど交流の経緯から版画や写真の作品が多い点、ポーランドとの交流が比較的進んでいる点などが挙げられる。
本展は、わが国で初めての東欧現代美術紹介の機会であっただけに、新鮮な印象で受けとめられたが、出品作品が平面作品に限られたこと、東欧の残る一国であるブルガリアの作品が出品出来なかったことなど残された課題もあり、わが国における知識のいまだ乏しい地域であるだけに、さらに体系だったかたちでの紹介が行われることが望まれる。なお、同展は横浜の神奈川県立県民ギャラリーでも開催された(2月20日~3月1日、主催:国際芸術文化振興会)。