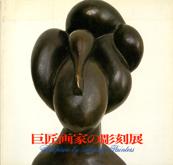会期:1979年5月26日~6月24日
本展は、19世紀から今日にいたるヨーロッパの巨匠画家27人の彫刻をあつめたユニークな企画であった。
19世紀の後半に、彫刻の世界は、ロダンの出現により近代への扉が開かれたといえるが、同じ頃にあらわれたドーミエ、ドガ、ルノアール、ゴーギャンらの画家達は、絵画的表現だけに飽きたらず、彫刻的表現にもその才能を発揮させた。このような試みは、マティス、ドラン、レジェ、ピカソ、ブラックらによってもなされ、今世紀の彫刻芸術に多大の影響を与えた。ロダンやロッソのドラマチックな表現の彫刻とは異なり、今世紀の彫刻は、造形の本質を追求し、造形芸術の実験的役割を果した。もともと、ヨーロッパの画家達にとって、彫刻を手がけることは少しも珍しいことではなく、むしろ、彫刻家による彫刻以上に造形の本質をとらえた魅力にみちた作品を創造している。このように、近代から現代の彫刻に革新と創造力を与えたのは、次々と新しい芸術運動を展開した画家達であった。
『わたしは、絵画と同様、土をいじって形を作るのが好きです。わたしはどちらでも結構なのです。探求することが同じなのだから。わたしが、一方の制作に飽きたら、こんどは別の方に顔を向ければよい。わたしは彫刻というものを、自分の思想に秩序を与えるための補足的な仕事だと思って制作しているのです。』これは、フォーヴィスムの巨匠マティスの言葉である。彼は、自然主義的な写実から離れて、大胆な量塊の組合せによる彫刻《ティアリ》(1930年)や《横たわる裸婦Ⅲ》(1929年)を制作し、その彫刻的な才能を発揮した。また、キュビスムの作家ではブラック、レジェが多くの浮彫を制作しているが、とりわけ多彩な彫刻を残したのはピカソであった。《妊婦》(1950年)、《女の頭部》(1951年)、《帽子を被る女》(1963年)などに、ピカソが平面・立体を自在にこなし、独自の造形領域を拡大したことを示している。
イタリアの未来派の作家ボッチョー二は、従来、空間の要素に重点を置いていた彫刻概念に、時間という新しい要素を導入して、立体造形の新次元を開いている。また、フォンタナは、絵画と彫刻との伝統的な境界を否定した作品を発表している。しかし、もっとも彫刻のもつ可能性を拡大し、彫刻の楽しさを提示してみせたのはシュルレアリスムの洗礼をうけた作家達であった。ジャコメッティ、アルプ、エルンスト、ミロ、ダリ、マッソンらは、絵画と同様に幻想的でユニークな彫刻を創造している。ジャコメッティの《腕のない細い女》(1958年)などの極端に細長い人体表現からは、人体を囲む無限の空間の拡がりを暗示させる。これらの作家達は、創造の源泉を精神の内奥(意識下の深層心理)に求めており、そこから生み出された造形は、自然の再現とは対象的に現実を超えた次元での創造であった。従って、本来は夢や想像の世界に属しているものが造形化されており、その彫刻に驚きとともに一種のユーモアさえいだかせる。画家による彫刻の造形-それは余技の境を超えて、彫刻芸術の革新をおしすすめたといえる。
会場は4階展示室を使用し、27人の巨匠画家の彫刻100点と、参考資料としてこれら画家の水彩、デッサンを展示した。また、当館所蔵のピカソの《肘かけ椅子に坐る裸婦》(1964年)、フォンタナの《空間の概念》(1961-62年)、デ・クーニングの《水》(1970年)、および、デュビュッフェの《群れつどう風景》(1976年)等の出品作家の絵画を参考陳列した。
なお、この展覧会は、上野の森美術館(4月21日-5月20日)をかわきりとして次に当館で開催し、引続き彫刻の森美術館(6月30日-8月19日)、神奈川県立近代美術館(8月25日-9月24日)、広島県立美術館(9月29日-10月21日)で展観された。