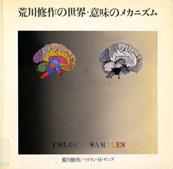会期:1979年7月5日~8月7日
この展覧会は、荒川修作の一連の制作である《意味のメカニズム No.2》から73点を紹介するために企画されたものである。
荒川修作は、1936年に名古屋で生まれ、武蔵野美術大学に学び、読売新聞社主催の日本アンデパンダン展に出品する一方、ネオ・ダダイスト・オルガナイザーズのグループを結成して、いわゆる反芸術的な造形運動を押し進め、特にセメントを用いた他に類をみないオブジェの発表によって世に注目された。
1961年末にアメリカへ渡った荒川は、以来ニューヨークに住み、渡米してからの造形活動は一変し、記号や日常の物体のシルエットによる図式的絵画表現を試みている。意味、記号性、イメージ、描法などをめぐる関係と、その認識のすがたを把握しようとする画面には、やがて巧みに言葉も併置されるように展開してきている。
荒川は1963年に西ドイツ・デュッセルドルフで個展を開いてのち、世界各地で相次いで発表を行い、ベニスビエンナーレ展、ドクメンタ展にも招待されるなど、国際的に高く評価されている。日本でも色々な展覧会に招待され、1966年の第7回現代日本美術展で大原美術館賞、1967年の第9回日本国際美術展で国立近代美術館賞、1968年の第8回現代日本美術展で最優秀賞を受賞している。
荒川の世界を紹介するこの「意味のメカニズム No.2」展は、マドリン・H・ギンズとの協力になる渡米初期の作品から最新作までを含み、今もなお未完ともいうべき言語と視覚の発生に遡って、絵画の明晰で厳密な体系化を試みたものといえる。この造形の表現構造の根底にふれる徹底性によって、次のように分類された一連の作は、荒川とマドリンを窮極の思想のモデルに向かわせていると思われる。
1. 主観性の中性化
2. 位置と移動
3. 曖昧な区域の提示
4. 意味のエネルギー(生化学的、物理的、精神物理的諸相)
5. 意味の諸段階
6. 拡大と縮少-尺度の意味
7. 意味の分裂
8. 再集合
9. 反転性
10. 意味のテクスチュア
11. 意味の図形化
12. 意味の感情
13. 意味の論理
14. 意味の記憶の構造
15. 知性の意味
16. 検討と自己批判
なお、この展覧会は今回とほぼ同じ内容で1972年に西ドイツで公表され、《意味のメカニズム(1963-1971の作品)》としてドイツ語の図録も出版された。昭和54年には、アメリカで1978年の作品を加えた英語版が刊行され、この展覧会のカタログ(日本語版)もそれによっている。