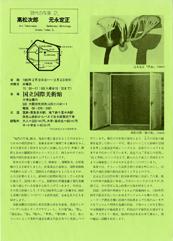会期:1980年 2月9日~3月23日
「現代の作家」展は、発表の場に恵まれることの少なかった日本の現代作家に、真価を存分に発揮できる機会を与え、その全容を広く紹介し、今後の現代美術の動向を探るために企画したものである。今回は高松次郎と元永定正の2人をとりあげた。いずれも国際的な問題意識で現代美術と取り組み、1960年代にその真価を高く評価され、現代も活発に制作しつづけている作家である。
本展では、4階会場に高松次郎の作品を、また3階・2階会場に元永定正の作品をそれぞれ展示し、作風の変遷および問題意識の変貌の諸相が一目で理解できるよう配置した。
1958年に東京芸術大学美術学部油画科を卒業した高松次郎は、〈点〉シリーズを開始するが、この時すでに従来の美術の範疇とは異質の芸術領域を探索しはじめていたことがうかがえる。それはハプニングやイヴェントに明確にあらわれてきて、1962年には赤瀬川原平、中西夏之とハイ・レッド・センターを結成し、日常的な社会にある種の変革をもたらそうとハプニングを行った。芸術と現実との世界の乖離を、独自の思考操作により超克し、そこに自らの芸術の世界を繰り広げようとする特質がこの頃すでに芽生えている。また、この作家の異才を不動のものとした〈影〉シリーズの端緒となった「不在性」の論理を確立しえたのもこの頃であった。1964年の〈影〉シリーズ、1966年の〈遠近法〉シリーズ、1968年の〈波〉・〈弛み〉シリーズなど、「不在性」の論理を武器に物の存在と視覚の問題をとりあげ次々に自己の概念芸術を展開しつづけていくことになった。しかし、高松の思考は、1968年の〈弛み〉シリーズを発表しえた直後を境として、また新たな創作原理にとりつかれた。それは〈単体〉・〈複合体〉シリーズ、「日本語の文字」・「英語の単語」・「題名」として発表されてくる。初期から1968年頃まで、不在性の観念を創作の原理として、あらゆる既成概念に挑戦し、それを超えた作品をめざしてきたが、この時期から、その観念は物質のある状態と人間との関係を提示する方向に向っていった。また最近では、空間シリーズともいえる〈柱と空間〉シリーズを制作しつづけている。これは、1973年からの〈平面上の空間〉シリーズの立体化である。このように、高松次郎の芸術は、独自の思考体系の展開過程に発生してゆく概念の芸術であり、今後最も注目される作家の一人といえよう。
元永定正は三重県上野市に生まれ、地元の日展系の画家浜辺万吉に就いて伝統的な油彩画を学び、フォーヴ風な色彩の具象画を描いていた。1952年兵庫県に移住し芦屋市展に出品するようになってから、抽象画に転向し、1955年発足間もない具体美術協会の会員となり、しだいに本格的な抽象画の世界へと入っていった。初期の平担で単純なフォルムの作品が、徐々にフォルムに流動性を加え、色彩に強烈さを増してくるのは、1958年ないし1959年頃からである。全く独自の発想から絵具をそのまま画面に流すことを始めたが、ちょうどその頃、日本中に吹き荒れていたアンフォルメルの潮流に触発され、たらし込みや流し掛けを効果的に多用した大胆な作品で、一躍日本のアンフォルメル作家として国際的に名を知られるようになった。1967年の秋、一年間のニューヨーク滞在を終えて帰国してからその作風は一変して、アンフォルメルの痕跡を留めない作品を発表しはじめる。明快なアクリル・カラーによる平板な色面構成を主体に、スプレーやエアブラシを使っての美しいグラデーションをみせる作品や、また、子供の落書を思わせる線描中心による作品など、ユーモラスなフォルムと明快な色調の作風へと変貌をとげて今日に至っている。本展では油彩画の他、版画とタピスリーをも展示し、この作家の全貌を一堂に紹介した。
なお、2月8日のオープンに際して、両作家によるイヴェントが、美術館で行われた。高松は1,000mの黒い紐がギャラリーから屋外へと展延してゆくものであり、元永はかって具体で行ったなつかしの煙のイヴェントであった。