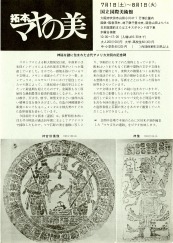会期:1978年7月1日~8月1日
この展覧会は、古代アメリカのマヤ文明が残したすぐれた文化遺産である石像や石碑などから写しとられた図様や文字の拓本を展示し、マヤ石彫のもつ造形表現の質の高さを拓本特有の白黒の美を通して伝えることを意図して企画された。
いうまでもなく、マヤ文明は、メキシコ南部からグアテマラー帯、ホンデュラス、エルサルバドルにかけて3世紀頃から数百年以上にわたって栄えた古代都市文明で、金属器もなく原始的な焼畑農業を経済的基盤としながらも、数学、天文学、暦学、神聖文学などに独得の高い精神文化を築きあげた。また、石造りの巨大で壮麗な神殿建築は、洗練された一種の様式美を示しており、壁面の浮彫や、神殿前広場に立ち並ぶ石碑や石柱の彫刻には、モニュメンタルな造形表現がうかがえる。
ピカソやブラックなどのキュビスムの作家達にアフリカ未開民族の素朴な造形感覚が、新しい表現を示唆したことはよく知られているが、古代マヤ文明の残した芸術的遺産は、シケイロス、オロスコ、タマヨなどの現代メキシコの作家達だけでなくヘンリー・ムアのような作家にまで広く影響を与えている。日本でも、北川民次や利根山光人など、その独得な魅力にひかれている作家は多い。
伝統的なヨーロッパの芸術観とは異なった世界を我々に教えてくれるこうした古代マヤ文明も、今日その遣跡の多くは、盗掘や破壊にあい、ジャングルの奥深くに荒れるがままになったものが多い。松本市に住む平川明氏は、初め石仏などの拓本制作でその技術を確かなものにした後、1967年以降、数回にわたってメキシコ、グアテマラ、ペルーなど中南米に渡り、現地に残された古代アメリカ文明の遺跡を訪れては、石碑や石柱の拓本を採り続けている。その正確な拓本の技術によって実物大に再現された、神聖文字や神宮像などの拓本は、亡びゆく文明の姿を今日に伝える記録として貴重なだけでなく、学術資料としても、各国の研究者達の役にたっているという。彼が今まで採り集めてきた、これらの拓本の中から、今回はティカルやセイバルなど最盛期のマヤ遺跡から採取された拓本45点の他、マヤ文明に先行し、その成立に影響を与えたといわれるイサパ文化の残した石彫を紹介する拓本12点、マヤ文明と並行して栄えたコツマルワパ文化の遺跡から採られた拓本35点、計92点の拓本を展示した。なかでも、コツマルワパ文化の残した巨大な石彫から採られた縦3.42メートル、横3.75メートルに及ぷ神官供犠像の拓本は、写真複製からは得られぬ迫力があり、圧巻であった。
古代マヤ文明の全体像について理解を深めてもらうため、会期中、NHKが制作編集した「マヤ文化の遺跡」のビデオ・フィルムを放映した。また、カタログには、マヤ石彫の拓本をB2版の大きさに複製したものの裏面に、出品リストや解説などを載せることにした。解説には、中南米の古代文明の中におけるマヤ文明の歴史的、地域的な位置について、研究者の立場から文化人類学者の増田義郎氏に「マヤ文明の系譜」という題でわかりやすい小論を、また、マヤ文明の不思議な魅力について、小説家の小松左京氏に「マヤの美に魅かれる」と題した一文を、それぞれ執筆いただき、本展鑑賞の一助とした。