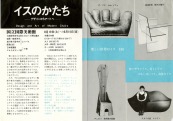会期:1978年8月19日~10月15日
当館の設立目的のひとつに現代美術(デザインを含める)の展示というのがあり、今回の展示はそのデザインに関する最初の企画である。
現在のわれわれの生活は近代工業の産物の上になりたっており、そこから生ずる多種多様な製品の相貌は美的観点からのみならず、社会的風俗的観点からも興味ある現象となっている。それは1920年代に始まった合理主義的な機能美追求のあとを受けて、大衆の様々な要求に答えるという形をとったためでもあって、全体としては脱機能主義ともよべる現象である。
本展はこのような傾向をもっともよく表わしている内外のイス110点と、芸術家の夢みるイス15点、それとデザイナー、建築家の皮肉なイス25点の計150点を選んで、この現象をさまざまな角度からとらえようとした。
会場の導入部はスチールパイプや木(合板を含める)、プラスチックスという材料の特性をうまく生かしたイスの展示から構成され、まず合理的機能なイスの思考を提示した。その分野ではマルセル・ブロイヤー、マルト・スタム、ミース・ファン・デル・ローエ、チャールズ・イームズ、エーロ・サーリネン、アールネ・ヤコブセン、ブルーノ・マットソン、アルヴアル・アールトらの近代デザインの古典的なイスから、ヴェルナー・パントン、クォフィ・チャン、エーロ・アルニオ、ヨー・クッカプーロらの余裕あるイスまで含められる。なかには新しい傾向の事務イス、例えば人間工学的なフォルムのヴィトラマット、形式主義的なデルタ、カラフルなソットサスなども加えた。
ついで、こうした合理性のあとをうけて、それから逸脱し、もっと自由な発想のイスを主に展示した。この分野ではイラストからぬけ出たタロンのイス、人体の形そのものを形成させたイス、空中で自動的にふくらむペーシェのいす、大小の円環をいくつか並べて坐らせるコロンボのイス、袋の中にプラスチックスの小粒子を入れて坐ったままの形をとることのできるイス、エレメントを横に並べて連結したソファなどがあり、この分野ではイタリアのデザイナーの活躍がめざましい。中には唇のイスやグローブのイスなど、いささかキッチュふうのものもある。
こういう面になると芸術家の発想はきわめてユニークで、カンナでけずる前の板で背の高い素朴なイスをつくったチェローリ、椅子の半分が布となったり、真中から半分に割れたりして驚かせるサマラス、あるいはソファーを男根ふうの布のつめもので覆いつくした草間弥生、つめたい鋼板でイスの実在感を明示する村岡三郎等、見る者の注目をひいた。
またイスをガラスで透明にした倉俣史朗、同じくミースのいすなどをガラスでパロディ風にまとめた葉祥栄、マリリン・モンローの身体から曲線をひき出して背とした磯崎新などの試みも関心を集めた。
全体を通じて、イスの多様なあり方は見る人を強く印象づけたようで、好評であった。また、全体の約4分の1のイスは、出品者の協力をえて観客に坐ってもらったが、これも好評を博した。
別に会場ではカナダのノーマン・マクラレン、久里洋二のビデオを放映し、多くの観客の足をとめた。