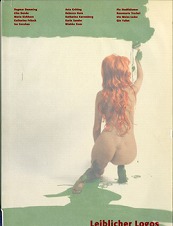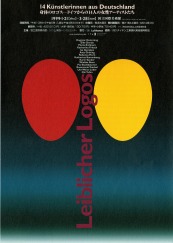会期:1999年 1月21日~3月28日
この展覧会はフランスの思想家ジャン=フランソワ・リオタールの次の言葉に触発されたものである。「男たちは−−少なくとも西洋では−−愛ではなく勝利を好む。男たちのもとでは、肉体、感性、匂い、接触、排泄、なるがままにまかせること、音色への皮肉な蔑視が支配的であり、これらに身を任せる者のことを『芸術家』と呼ぶ。芸術家は女性的である」。14人の女性アーティストたちは以上のような動機ゆえに参加することに同意した。こうしたことから本展の背景には「女性による芸術」というものの存在への問いかけがあり、また芸術家の中にある「女性的性格」を女性の芸術家の作品をとおして探ろうという意図があった。
また「女性」をキーワードにした本展の背景には、思考に関する次のような今日の一般的な見方があります。つまり、ロゴスすなわち理性を頂点に置き、身体や感性をそれより低く位置づける思考が長らく西洋では支配してきたが、今日この思考形態は崩れかかり、それに代わり非理性的・女性的なるものが正当化されてきているという見方である。そして事実そうした時代にあって今日のアーティストたちは身体的・感性的なるものに価値を見出してきているので、この企画は時代の流れに即したものと言うこともできる。
他方では70~80年代には少数派だった女性アーティストがドイツでは確固たる地位を築いているが、ドイツ国外では彼女たちの作品が十分には紹介されていないので、その情報の欠落を埋めるという目的を持っている。
出品作品は美術における身体性・感性を強調しようという意図から、いわゆる絵画・彫刻は慎重に避けられており、オブジェとインスタレーションが中心に構成された。またそうした作品選定は90年代の美術動向を反映したものにもなっており、2000年を目前にして1990年代の美術を振り返る好機でもあった。
なお本展は栃木県立美術館に巡回した。
出品作家 ダグマー・デミング、エルケ・デンダ、マリア・アイヒホルン、カタリーナ・フリッチュ、イザ・ゲンツケン、アスタ・グレーティング、レベッカ・ホルン、カタリーナ・カレンベルク、カーリン・サンダー、ヴィープケ・ズィーム、ピア・シュタットボイマー、ローズマリー・トロッケル、ウーテ・ヴァイス=レーダー、秦玉芬