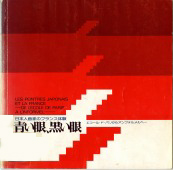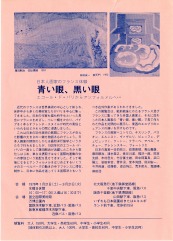会期:1978年1月21日~3月21日
本展は1920年代のエコール・ド・パリからアンフォルメルを経て70年代にいたるまで、約半世紀にわたる日本人画家のフランス体験の諸相を、作品に即して展望しようとしたものである。展示は日本人画家23名、68点と、同時代のパリで活躍したヨーロッパの画家13名、31点によって構成された。
黒田清輝が外光派風の写実主義を移入して日本近代洋画の道をひらいて以来、パリに渡る多くの青年画家たちの目的は、師についてその様式、技法を学びとり、それを日本に伝えて第一線で活躍することにあった。このいわゆる洋行留学のパターンは、20年代に、藤田嗣治がエコール・ド・パリの一員として認められるあたりから、国際舞台への参加をめざす次の段階へと移り、本展もそこを出発点としている。藤田は、なめらかな乳白色の地に日本画の面相筆の線を走らせる独自の画風の創出によって、一躍、パリ画壇から国際的に名を知られるようになった。
ついで1924年に渡仏した佐伯祐三は、フォーヴィスムの洗礼によって近代絵画に目ざめ、30歳で客死するまでわずりか3年のフランス生活のうちに、憑かれたように自らの世界をつきすすんだ。
ブルトンの「シュルレアリスム宣言」が出された1924年にパリに渡った福沢一郎は、この運動に傾倒して、31年の独立美術協会第一回展にはパリから37点の作品を送り付け、シュルレアリスムの日本への本格的移入として強い衝撃を与えた。一方、カンディンスキー、モンドリアンらの主要な抽象画家たちが32年に結成したグループ「抽象・創造」には、岡本太郎が参加したが、やがて形式主義的なこの運動と別れて、彼もまたシュルレアリスムに接近し、パリの国際シュルレアリスム展に出品している。
日本での銅版画技法に限界を感じた長谷川潔は、1918年フランスに渡り、パリに定住して、ヨーロッパで絶えていたメゾチント技法を研究復活させ、その精妙な黒の諧調による表現とイメージの象徴性によって注目されるようになった。
第二次大戦後は、田渕安一、今井俊満、菅井汲、堂本尚郎らがいち早く渡仏し、50年代のアンフォルメル運動の渦中に身を投じている。以後、田渕は近代的なカラリストとしての素養から、逆に日本や中近東の民族的な色彩を象徴的につかみ、菅井はシステマティックな客観性の方向へと制作をすすめる。堂本は途中でアンフォルメルとの越えがたい溝を意識して明確なフォルムを共通言語としてさぐり今井の方は「アンフォルメルの日本の旗手」として活躍するなかから執拗にイメージの転回をとげてきた。かれらの後に、麻田浩、岩田栄吉、平賀敬らがつづき、国際化社会の中で渡仏の意味を大きく変容させながら問題を今日につないでいるわけである。
展示にあたっては、時代と運動の流れに沿って「青い眼、黒い眼」の作品を対照させ、東西のエスプリのニュアンスを明らかにするように留意した。